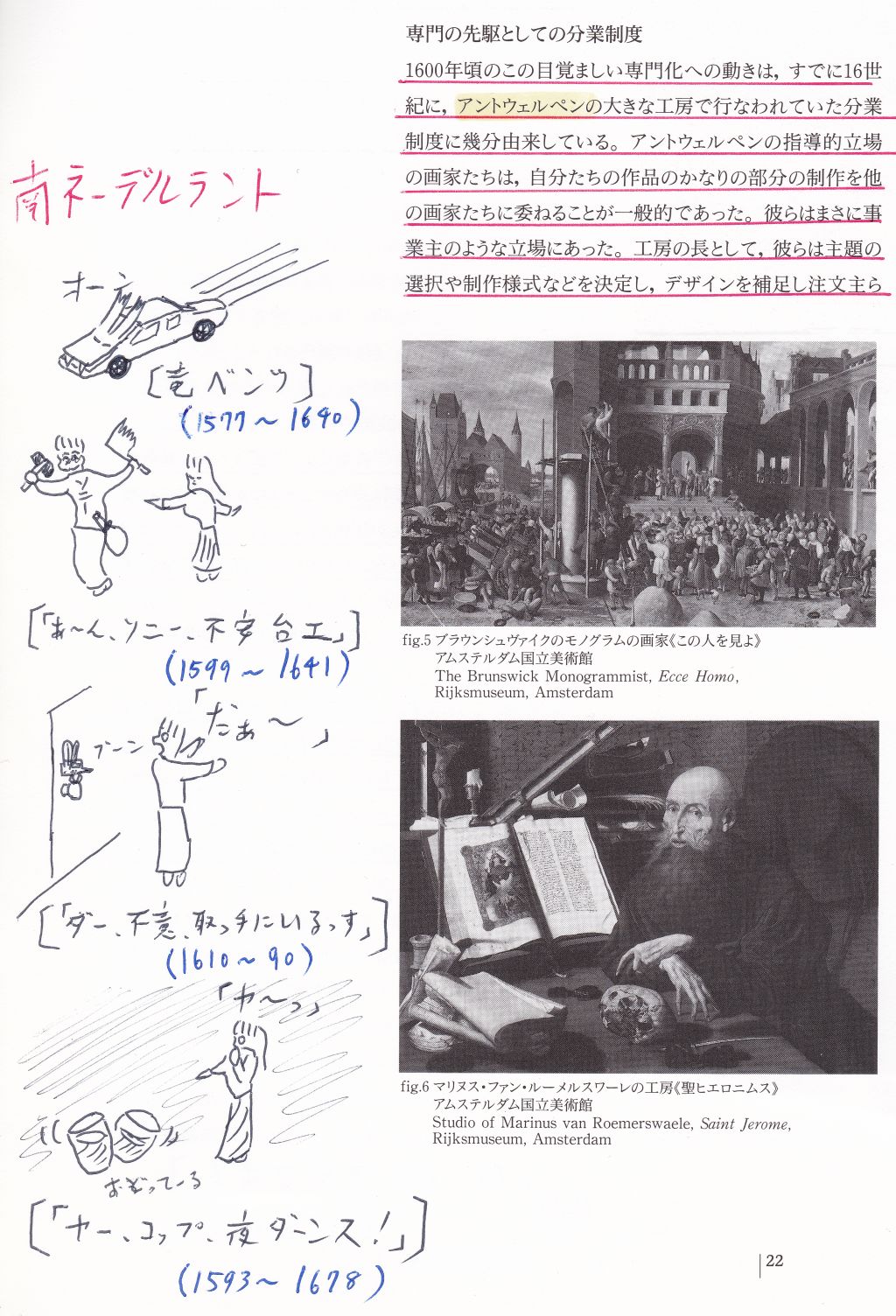レンブラント、フェルメールとその時代展
サブタイトル――「アムステルダム国立美術館所蔵17世紀オランダ委美術展」
開催期間――2000/7/4~9/24
開催場所――国立西洋美術館(上野)
主旨
2000年の記念すべき年に、日蘭交流400周年の記念行事として、アムステルダム国立美術館の全面協力の下で17世紀オランダ絵画展を開催。風景と風俗、肖像画と静物画という写実性と日常性だけのオランダ絵画という誤った見方が急速に見直される中、改めて全体像を見直してくださったらこれ幸い。
Ⅰ 黄金時代の曙
ブルゴーニュ公国領ネーデルラント地方は、複数民族、複数都市国家的なまま、経済圏と文化圏を共有し続けたが、ハプスブルク領となり、北部を中心にプロテスタント信仰が浸透。フェリペ2世のカトリックの強制や中央集権的制作から、1568年独立戦争が勃発。1581年には北部7州がネーデルラント連邦共和国(通称オランダ)として独立を宣言。イギリスの協力もあり17世紀に入る頃には、事実上の独立を果たしていた。
その間、アントウェルペンは没落し、アムステルダムが経済・文化の中心地としての地位を確立。絵画においては、ファン・マンデルが「絵画書」(1604年)を出版し、美術のアカデミーを作るなど、オランダ絵画の基礎を築いた。ただ最初の中心地はハールレムからはじまった、として絵画の紹介が。
ヘルクレス・ピーテルスゾーン・セーヘルス(1589/90-1633/38)
「渓谷」(1620頃)

・油彩画は11点ほどしか残されていないが、エッチング(版画の一種)で知られたセーヘルスの作品が、エッチングの方にも展示されていた。
ヤン・ピーテルスゾーン・サーンレダム(1565/66-1607)
「ベーフェルウェイクに打ち上げられた鯨」(1602)

・1601年のマッコウ鯨死体の打ち上げの様子で、悪い予兆とされていた。下にはこの頃の日食や皆既月食、地震などの不吉か記されているそうだ。
Ⅱ オランダの景観
17世紀オランダの美術史における功績は、風景画という独立したジャンルを確立したことであると説明がなされている。その基礎はヨアヒム・パティニール(c1480-1524)によって築かれ、はじめの成功者はヤン・ファン・ホイエン、完成させたのはヤーコプ・ファン・ライスダールであるなど解説されていた。また都市の景観図も、地図製作と共に盛んなど。

・[「よぉ」「あっ」「ひっ」「むっ」パーティーにいる!]でヨアヒム・パティニールを表現したというあやしい暗記術。
エマニュエル・ド・ウィッテ(1616/18-1692)
「ゴシック様式のプロテスタント聖堂」(1669)

・オランダは、花の画家、肖像画家、など専門分野の細分化が著しかったが、彼は建築画家として知られることに。もっとも建築の具体的表現より、切り取った構図の「インスタ映え?」を目差している。
ヤーコプ・イサークスゾーン・ファン・ライスダール(1628/29-1682)
「ハールレム眺望」(1670頃)

・オランダ黄金時代の風景画を代表すると紹介されていたライスダール。カタログの余白に「実際に見た時の大きさと明るさのトーン、バランス下でのほうが、はるかに優れて見える。ただし美術館の照明がどうあるべきか、それはまた別の問題です」という自分の当時の書き込みが。別の風景画の所では、こちらは実物と違ってカタログがよく見えるので、実物を見ない限り判断は出来ないという記述があった。
・そして書き込みと言えば、こんな書き込みもまた……
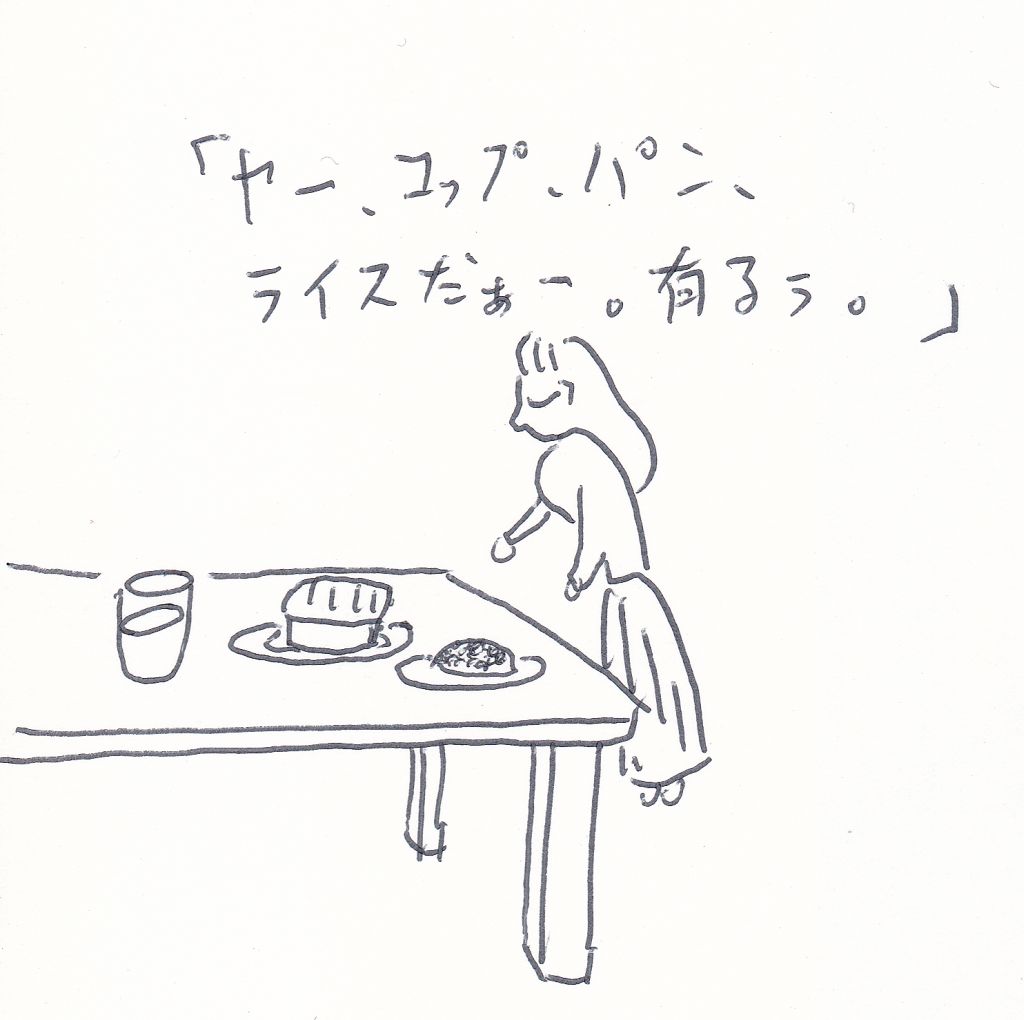
「嫌(やー)、コップ、パン、ライスだぁ。有るぅ。」(意味不明)
ヤン・ファン・デル・ヘイデン(1637-1712)
「アムステルダムの運河―空想的光景」(1670頃)

・1668年にガス灯が夜の街路を照らす史上初の都市となったのも、その7年後に運河の水をくみ上げてホースで放つ消火活動をはじめたのも、彼のおかげであるという解説によって、記憶に残されている絵画。複数の場所を組み合わせたので「空想的光景」
メインデルト・ホッベマ(1638-1709)
「水車小屋」(1670頃)

・「ミッデルハルニスの並木道」で知られた風景画家の彼は、ヤーコプ・ファン・ライスダールに師事。当時水車は最先端の技術だったのだそう。
Ⅲ 静物画の世界
「静物画」は古代から存在してはいたものの、オランダでは17世紀初頭から、静物画の割合は増加しつつ、歴史画などが減少していく。17世紀以降もっとも多く描かれたのは風景画であると解説にあった。そしてリアリズムの探求と共に、この世のむなしさ「ヴァニタス」という影のテーマが、もっとも反映されたのも静物画であったとか。
ヤン・ダフィツゾーン・ド・ヘーム(1606-1683/84)
「本のある静物」(1628頃)

・書物、リュート(楽器)というモチーフも、書類のようなものに描かれた「Finis(おわり)」の文字も、17世紀オランダ美術で流行した「ヴァニタス(この世のむなしさ)」のテーマなのだそう。
ウィレム・ファン・アールスト(1627-1683)
「家禽(かきん)のある静物」(1658)

・死んだ動物を描いた静物画は、狩猟の獲物としての意味を持ち、アールストもその代表画家のひとりだったとか。死んでると思ったら、目が生きてるとか、そんなことを思って眺めたような気がする。
Ⅳ レンブラントと肖像芸術
歴史画を上位に置くヒエラルキーに変わりは無かったが、新興のブルジョワジーと、彼らの暮す都市が中心となったオランダでは、きわめて多くの肖像画が描かれることになった。多くの画家のいるなかで、フランス・ハルス、レンブラントなどの傑作が描かれていく。レンブラントがアムステルダムに移り住んで名声を確立したのも肖像画だし、「夜警(やけい)」はきわめてよく知られた市警隊の肖像画である。
フランス・ハルス(1581/85-1666)
「男の肖像」(1635頃)

・あまり見た記憶が無いが、謎の暗記術と一緒に。
ホーフェルト・フリンク(1615-1660)
「羊飼いに扮したレンブラント」(1640頃)

・レンブラントの弟子でもあったが、実際に本人を前にしたものか、自画像などを利用したものか不明とか。
レンブラント・ハルメンスゾーン・ファン・レイン(1606-1669)
「聖パウロに扮した自画像」(1661)

・パウロはプロテスタント世界で高く評価され、哲学、芸術、宗教において優れたメランコリー気質を特徴とすると解説にあった。
ヘルブラント・ファン・デン・エークハウト(1621-1674)
「片肘をついて寛ぐ男」(1650-60頃)

・筆画によるデッサンで、メランコリー気質を表わしているポーズとか。かつての知人のためには掲載しておかなければならないもの?
Ⅴ フェルメールと風俗画
風俗画もまた流行した。農村的であるより都会的傾向はあるものの、描かれる内容は多様である。特にフェルメールやピーテル・ド・ホーホらは、その代表的画家と言えるかも知れない。
ピーテル・ド・ホーホ(1629-1683)
「配膳室の女と子供」(1658頃)

・子供に渡しているのはビールで、当時は健康飲料として子供の飲めたとか説明があった。フクロウが釣りをして「引いてるど、ホーホー」と鳴いているという、例の暗記術も記されていた。なにをやっているのやら。
アリ・ド・ヴォイス(1632頃-1680)
「陽気なヴァイオリン弾き」(1660頃)

・19世紀半ばまでは高い評価を得ていたが、急に忘れ去られた画家のようだ。「レイデン精緻派(せいちは)」に近い作風とあった。ただそんなことよりも、ワインを飲んでいる陽気な人物に惹かれたらしく、「おやっさん」という落書きと、また無意味なイラストがカタログに書き加えられていた。ただ「名画」とあるのは、おそらくカタログを知人に見せるために、自分のイラストに加えられた冗談のようだ。何もかも霧のかなたの出来事ではある。
ヨハネス・フェルメール(1632-1675)
「恋文」(1668頃)

・なぜか、枠構造の手前部分の暗がりや、床の模様を眺めた印象が先に浮かんできた。
Ⅵ もうひとつのオランダ美術
クールベやバルビゾン派が目を付けて、写実主義のオランダという見方が定着してしまったが、歴史画などの伝統的ジャンルも描かれていた。その多様性こそがオランダ絵画であるということか。
パウルス・モレールス(1571-1638)
「美しき女羊飼い」(1630)

・神話の女神からの由来と、16世紀ヴェネツィアの高級娼婦画などから由来して、性的関心もとか解説されていた。
レンブラント・ハルメンスゾーン・ファン・レイン(1606-1669)
「オリエント風に装った男」(1635)

・肖像画に見えて、「トローニー(頭部習作)」といって、衣装や表情のプロトタイプのような絵画が、オランダでは下書きではなく、ジャンルとして存在していたという。この後、「レンブラントとレンブラント派展」の方に掲載してあるファブリティウス作かとされる「洗礼者ヨハネの斬首」の絵画が、この展覧会でも飾られていた。
ヘルブラント・ファン・デン・エークハウト(1621-1674)
「最後の晩餐」(1664)

・レンブラントの弟子の作品として、フェルディナント・ボルと、エークハウトの作品が飾られていた。しかも扉を卵が這い回っている絵が解説に落書きしてあった。「エック、這う戸!」と驚いている男の絵も描いてあった。アホである。
カタログの冒頭の解説
おまけとして
マリエット・ウェスターマンという人の解説が、要領を得ていたので、まとめてみたら、「総括」してから「具体的」に語り、オランダが需要に応じて専門画家を生み出していったこと、その多様性と問題点などを、展覧会とリンクさせながらうまくまとめてあった。ただし、下のはそれを簡素にまとめたものとは言い切れず、わたしが勝手に解釈したり、曲解したりした点も多かろうと思うのでただ参考のために。
むしろ注目点、あるいは問題点?は、わたしの描きまくった人物暗記術の方で、この強引かつおちゃらけた暗記方法は、知人との遊びの中で生み出されたものらしかった。同時にまったく画家を知らなかったので、手当たり次第覚えようとした名残でもある。このカタログほどそれが目につくカタログも、他にはなかったので、記念に?残しておくもの。これが全部ではないから恐ろしい。
総括的
17世紀はレンブラント、フランスハルス、ヨハネス・フェルメールといった天才を生んだオランダ絵画の黄金時代だが、もちろんそれに留まるものではない。当時500万人ほどの人口に対して数百万点の絵画が制作されたと思われるくらい、都市と市民という新しい階層ばかりでなく、貴族から農民にいたるまで、自宅で絵画が飾られるほどだった。
このような需要に応じて、画題の細分化、専門化が進んだが、それはそれぞれの画家の特徴ともなり、また得意ジャンルに生きられるという利点を見いだす側面もあった。例えば今回出展されているエマニュエル・ド・ウィッテはもっぱら教会内部を描く画家であったり。そんな中、レンブラントは様々なジャンルを扱う点において、むしろ例外的と言えるくらい。
具体的
カトリックの伝統から、宗教画こそが絵画であった時代から、プロテスタントの聖書回帰運動の高まりが、支配者への反発と結びついて、1566年には聖像破壊運動(イコノクラスム)がネーデルラント中に広まった。これによって宗教的な美術品の多くがこの世から消えてしまったのだった。1568年からは八十年戦争と呼ばれる戦乱が勃発し、その中でオランダが独立を果たすという流れになる。
そんな訳で、南部はカトリックに留まり、破壊された作品の復旧や、新しい宗教的作品が生みなされた。もともとネーデルラントでは大規模な工房で、分業体制によって絵画をしたてる伝統があったが、南部はその伝統は継続され、工房を取りまとめる画家としての、ピーテル・パウル・ルーベンス、アンソニー・ファン・ダイク、ダーフィト・テニールス、ヤーコプ・ヨルダーンスなどが活躍。
一方北部でも、当初は教会外からの受注により、聖書や神話の絵画がメインであり続けたが、1600年頃を境に、絵画の専門家と、市民購入という新しい関係が整えられていった。信仰の自由と共に、そのような工房という体制からの離脱を求め、あるいは覚悟して北部に流れた画家たちは、新しい道を模索する。北方のヴァザーリを自認するカーレル・ファン・マンデルはその『絵画書』のなかで、ミヒール・ファン・ミーレフェルトについて、時代が彼を肖像画家にしたことを記している。
専門分野といっても、執筆傾向、あるいは主義的なものから、画題によるものまで様々である。1625年頃から活躍したレイデンの「レイデン精緻派」とよばれる画家たちは、入念な細部描写という点で共通していた。地中海風の明るい風景画を描いたヤン・ボト、ニコラース・ベルヘムらは新イタリア派と呼ばれている。ヤン・ステーンの作品はそれよりずっと幅があるけれど、陽気な人々のつどいや、にぎやかな風俗画を描き出す点でひとつの職人芸的であり、聖書が主題となってもその傾向は変わらなかった。そういう点で見ると、レンブラントもまた専門芸であるといえる。(というのがカタログの解説のもって行き方だったが、まとめるために意図的にそそのかされた気がしなくもない。)
それに対して、風景画ばかりを描き続けたヤン・ファン・ホイエン、建築画のピーテル・サーンレダムやエマニュエル・ド・ウィッテ、鳥の絵画を専門とするメルヒオール・ドンデクーテルなどは、自らの画題を専門化することによって、人々から認知され需要を得る事が出来た。ウィレム・ファン・ド・フェルド(父)の海戦画はマニアックな好奇心に答えるものだったが、同名の息子の海景画は絵画としても魅力を持っている。
この後、もっともこの傾向が、賞賛されたかは別問題で、批評家や美術家は理想と現実の中でゆらめいたような解説から、紋切り型や専門画過ぎる弊害もあったという最後の部分を抜けて、にも拘わらず多様な魅力と締めくくられていた。