啓蟄(けいちつ)
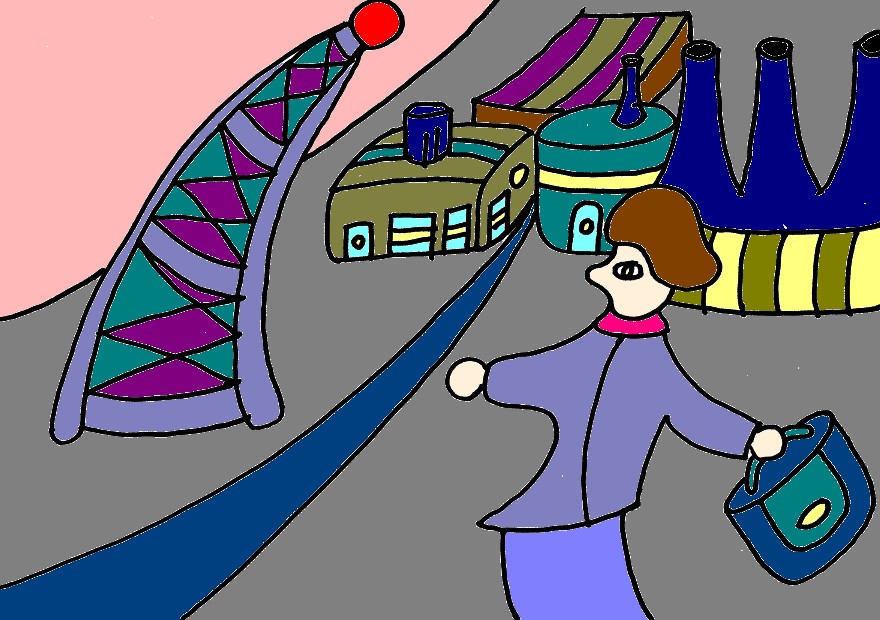
空はこんなに深くて静かなのに、眺める啓司(けいじ)は追い込まれるのを感じた。風の音が、確かに自分をあざ笑っている。早すぎる春の気配を闇に帰そうとする西空に、鉄塔の赤いシグナルが瞬いている。彼はそれを、燃え尽きた血潮だと錯覚した。夢はもう、終わったのだと思う。つまらない人生だった。楽しいことなんて何もなかった。生まれてさえ来なければ、静かな分子の深層のまどろみの中、組み立て工場の製品化されないで、分離されたまま漂っていられたなら、幸せだの不幸だの、そんな情感など知る由もなかったのに。哀しみなんて言葉を、覚えなくても済んだはずなのに。
靴音近くをつむじ風が抜けていく、その冷たい自由が羨ましい。
啓司は、穢された心が、濾過(ろか)し得ないことを知っていた。社会へ対する憎しみが、青年の頃のすがすがしい屈託のなさを打ち砕いて、どんなに修繕を重ねても、塞ぎきれないことを知っていた。
「こころの中が真っ黒だ」
啓司は呟いた。
けれども彼には、慰めてくれる知人など、もはやどこにもいなかった。長い歳月が、理解し合える人間など、この世に存在しない事を教えてくれた。いや、あるいは母国語が異なっていたら、学生の頃、英語を習得していたら、国を逃れて、まるで異なる理想郷……そこまで夢見ないにしても……少しはマシな社会が、開けていたような気もする。今はすべてが虚しい。懸命な期待や努力が、諦めへと移り変わった時、更けゆく宵をさ迷う寂寞に、彼は取り込まれたらしかった。
満員列車がカンカンと、車道を押しとどめながらに過ぎる頃、工場街を逃れた証明みたいに、ビル街が両脇から迫ってくる。すぐ先のステーションは、くすんだ外装をまばゆい照明に誤魔化しながら、人々を吸いこんでいくように思われた。四方から現れるサラリーマンに挟まれて、啓司もその中へと消されゆく。携帯をかざすと音がして、改札口をすり抜ければ、流れ作業をした階段へと運ばれていくのだった。
プラットホームのひしめきは、鶏小屋の密集か。
ただ鶏と違って、「コッコ」と鳴かないから、むっつりとして騒がしい。総体に疲れ切っている。それでいて落ち着かない。理性が後退したいらだちと倦怠が、充満する檻の中にいるようだ。それで罵り合うものもなく、狂化して路線へ落ちる者もなく、毎日を平然と乗り切っていけるのは不思議だ。いくら人間が従順だからって、これほど詰め込まれて平気なのは、自他に差分のない規格品の証明ではないか。啓司は恐ろしくなってきた。
平和なメロディーを共として、危機感のないアナウンスが響いてくる。右手に持った鞄が重い。仕事の資料なんか持ち帰らなければよかった。自分の憐れな忠犬ぶりを、尻尾の振りざまを見せられたようで、何だかやりきれない。ほどなく列車は止まる。ドアが開く。押し出された人だかりと入れ替わったとき、啓司もまた列車の人となった。
契約の誕生より早く、存在すべき人間の自立的価値。
そんなものは、言語動物である我々には、定義しきれないのかもしれない。だが例えば家庭は企業ではないはずだ。数家族が寄り添うくらいの役割分担にしたって、その小社会を、直ちに大社会の規格に捉える必要はない。そして、人間の根源価値は、大社会ではなく小社会のなかにこそ、まずは存在すべきではないのか。そこまで、引き戻して考えた場合、今の我々の生活は、真に正しい精神を保っているのだろうか。それとも、知らずのうちに魂を食い殺されて、充填されたプログラム、人の形をした既製回路、それな同一基板に代えられてしまったのではないか。だからこそ、これほど密集しても、輪を乱すこともなく、秩序を乱すこともなく、平然と仕事を続けられるのではないか。満員列車に毎日揉まれていると、不気味な不安が高まってくる。魂を喪失するような不安が。田舎へでも引っ越せたなら、これほど切迫した危機感も、遠ざかって人間性を、回復することが出来るだろうか……
列車が駅に到着する。
商品の入れ替えみたいな乗り降りが完了するまで、目の前のサラリーマンの携帯が、視線から離されたまま文字を連ねていた。メールの最中らしい。啓司は扉の封鎖を待っている。ドア付近では自(おの)ずから悟りきって、プラットホームへ下り立って、最後から乗り直す人影もある。それが礼節やマナーではなく、プログラムされた装置のように、啓司には思われた。契約的な規律がこの都市を支配している。それに合わせて、自分は魂を無くしかけている。しかし順応すべき人々が、怯える自分よりまっとうであるとは思えない。もし広範の信任を得た思想が常に正統であるなら、人類は有史以来の経歴をこれほどまでに、戦争に費やしたりはしなかったろう。それゆえ少数派の意見は常に社会にとって必要であり、多数派の意思のみを是(ぜ)とするような社会は、常に単一的無思想の危険にさらされる……そんな下らないことを考えながら、彼は吊革にぶら下がっているのだった。
「ある時、鶏(にわとり)と飼い犬が話しをしました」
不思議な情景が胸に閃いた。
取り留めもない妄想が、揺られまぶたの列車の子守歌となって、疲れ切った神経を雨だれみたいに宥めるとき、彼は思考とも夢とも定かではない、奇妙なイメージを心に満たしたのである。

ある時、鶏(にわとり)と飼い犬が話しをしました。
「俺たちは似たもの同士だ。人に飼われて、餌を貰って、そうして自由を奪われていやがる」
「君はそこから出たいの」
飼い犬が、飼育小屋の鶏に尋ねます。
「出たいに決まってるじゃねえか。柵が壊れたら、外へ逃げ出してみせるんだ」
「外へ出て、生きていけるの」
「当たり前だ。俺はいつだって憧れてるんだ。奴隷みたいに、ぎゅうぎゅう詰めにされて、毎日卵を産まされるなんて割に合わねえ」
「だって、ぎゅうぎゅう詰めって、君たちみんな、毎日々々井戸端会議で、大はしゃぎしているだけじゃないの。与えられた卵作業だけ、していれば餌を与えて貰えるからってさあ。僕なんかよりよっぽど、ぐうたらに眠り呆けているじゃない」
「なんだと。俺たちに自由意思はないとでも言う気か」
「うん。はっきり言わせてもらえば、繋がれているのは事実だとしても、繋がれていない環境じゃ、生きていけないんじゃないのかなあ。インコと一緒でさあ」
「うるせえ。そんなこと言ったら、お前だって一緒じゃねえか」
「そんな口調はよそうよ。僕はね、もともと野良だったんだ。街へ出ても、餌を見つけられるし、危険を察知すれば逃げ延びる自信だってある。いざとなったら噛みついてやるしね。この鎖はね、だから隷属の鎖じゃない。ただ僕が僕の意思で、ここの主人に仕えようと決めたから、進んで契約を結んだだけのことさ」
「嘘を抜かすな。奴隷は奴隷だ。何も変わらねえ」
「だって、君たち。もし柵が破れたら逃げ出すだろう」
「あたり前じゃねえか」
「でもさあ。逃げ出して生きていかれると思うの」
「俺たちに生存本能が、無くなっているとでも言いやがるのか」
「うん、言っちゃ悪いけど、そう思う」
「てめえ。黙って聞いていれば、つけあがりやがって」
「まあ。落ち着いて話しを聞きなよ。だいたい君は、生まれたときからそこにいるんだろう。どうやって自由社会で生きていかれるのさ。自然に置かれた状態で。だいたい、君、空を飛べるの」
「そりゃあ。お前、いくらだって……これから、そうさ、外を出てから、どうにかしてやるのさ」
「それは無理だよ。子供のうちの慣習は、絶対的に一生を規定してしまうんだ。人だって動物だって一緒さ。だから未成年のうちこそ、一生分の命をそのものらしく生き抜くために、餌やらおしゃべりやら娯楽一辺倒に溺れさせないで、つまりべらべら鳴き声ばかり空元気で、いつも誰かと横並びにくっついていないと落ち着かないくせに、実際の行動は卵を産むくらいしか出来ないような、ちっぽけな規格品にならないために、あらゆる皮膚感覚と肉体の記憶を懸命に知性と結びつけて、幼い頃の僕みたいに、例えゴミ箱をあさってでも、人間の子供を手なずけてでも、実際に行動して生きてみなかったら、もう大人になってからでは、規格品にしたがった生き方しか出来なくなってしまうんだよ」
「つまり、俺がここを出ても、今さら生きられねえとでも言うつもりか」
怒り出すかと思われた鶏は、急に消沈してしまったようでした。
威勢はいいのですが、実際は四六時中檻の中にいて、犬と体を付き合わせたことすらない臆病者ですから、偽物の口調にはすぎないのです。つまりはほんの小者であり、そのうえ図星のところを指摘されたものですから、どう答えていいか、分からなくなってしまったのでした。
「だからさ、半分は仕事をこなしてこき使われているんだけれども、一方では圧倒的に社会に守られているんだよね。そうして、そこを離れては、詰め込まれた檻の中で卵を産むという環境以外では、君たちはもう、何ものとしても行動できなくなっているのさ。それでいて、外を羨ましがっている。何か、違っていると思うけどなあ。あるいは君たちは、羨ましがっているものを手に入れる気なんか毛頭なくって、ただそのことについて、べらべらしゃべりたいだけなのかもしれないね。だからいざ柵が壊れたときには、やっぱり躊躇して、小屋の中に留まっているんじゃないかなあ」
「だって、お前だって……」
「僕は時々、鎖だって外して貰える。だから、その気になれば、走って逃げることだって出来るんだ。もし主人が気に入らなければ、本気で差し違える気があるならば、その後の処刑は免れないにしても、首に全力で噛みついて、殺すことだって出来るかもしれない。それでいて、首輪を苦にもせず、彼に従っているのは、それが僕の選択した自由意思であるがゆえにであって、隷属とはまるきり別のものだ。よく、忠犬だなんて、馬鹿にする奴がいるけれど、あれは違っている。僕らの忠義は真に自発的なものだ。自発的というのは、つまり、労力に見あう対価や、賃金や、安定や、餌を求めて忠義を示しているんじゃないってことさ。あのだらしのない人間どもの、職場でみせる忠義とはまるで違っている。だから奴らが、『忠犬みたいに職場に隷属して』なんて言うのは本当に腹が立つ。忠犬は職場になんか決して隷属しない。職場は仕事をして対価を得るための施設だからね。それは愛情を注ぐ生身の相手とは、区別されべき存在だからね。それを、企業に隷属して規格化された部品になっているにも関わらず、会社のために自発的に行動してなんてほざくような誤認症と一緒にされるのは、我慢がならないのさ。
だからね、たとえ僕が君の立場で、餌を得るために、卵を産み続けたからといって、いざというときに身を挺して職場に奉仕したりなんかしないよ。だって、子供に育てられない卵を産み落とすなんて行為に、精神を注ぐべき価値がある訳ないじゃない。誰かのための親切じゃなくって、利潤を生み出すことが最終目的の行為に、忠節を尽くす価値なんかあるわけないじゃない。僕はそんな真似は決してしない。けれども自由意思に基づく、あるお気に入りの誰かのためになら、それが組織でなく、人と人の、あるいは犬と犬の、あるいは人と犬の、一対一の関係から成り立つような、愛情の関係で結ばれているのならば、僕はどんな忠義だってまっとうしてみせる。自分の意思として献身を貫いてみせる。
だから僕ら犬というものは、人間よりも、君たち鶏よりも、そうして奉仕の気持ちを持たない猫なんかよりも、よっぽど自由の精神を、孤高の旗印を、胸に秘めているものなんだ。だいたい君たちは、いろいろ言っているみたいだけれど、一体に、待遇の改善を求めて、全員一丸となってストライキをでも敢行することすら出来ないじゃないか。ただ酒を飲んでは愚痴って、でも本当はその小屋の中が、安楽で、安楽でたまらなくって、そこから逃げ出すなんて、思いもよらないんじゃないのかなあ」
鶏は、もう答えませんでした。そうして、夜になるまで、自分はこの小屋から、本当に逃れるだけの勇気は、持ち合わせていないのかしら。こっそり涙を流しながら、仲間たちのおしゃべりにはもう加わらず、一羽でもの思いに耽っているのでした。
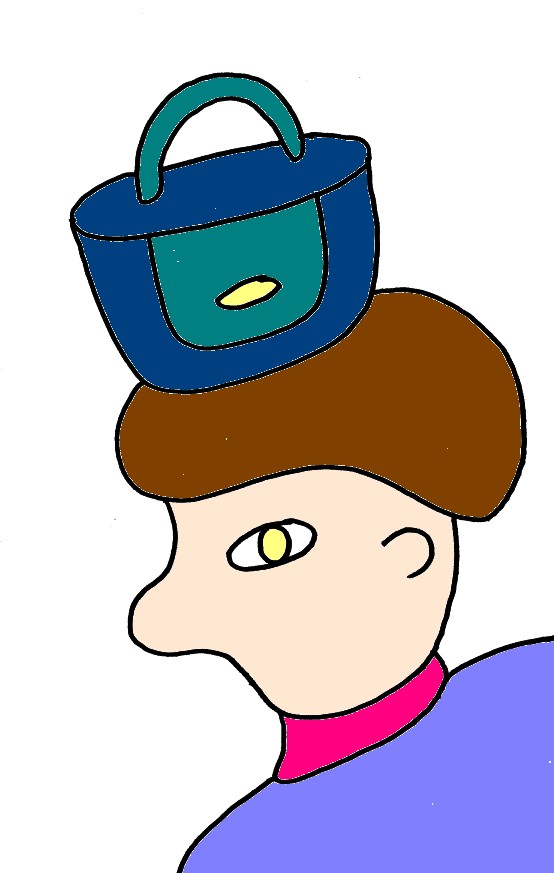
がくんと首を折って驚くと、
啓司は満員列車に揺られていた。
鶏の寂寞が押しよせてくる。
それにしても……
こんな奇妙な童話を夢想するなんて、よほど鶏へのシンパシーが募っているに違いない。ぎゅうぎゅうの吊革は横一列に空きがない。そうして、みんな俯(うつむ)いている。つり下げ広告なんて見る者もいない。ただ遠くの学生だけが元気である。化粧の崩れかけたOLが侘びしそうに首を折る。ここにいる誰もが、鶏のような生活を送っているとして、いや、それが仮に半数だとして、自由の旗を掲げて逃亡を決意して、駆け出せるだけのバイタリティーを持った奴が、何人くらいいるだろう。そうして、自由意思を信任する者が少ないほどに、なおさら小屋を逃れる孤独者は、支援もなくて滅びゆく一方なのではないか……
啓司には不意に、暖を取る護送列車のハウス栽培で、レールに従うことのみを、規格に従うことのみを讃える、この国の教育システムが、おぞましいほどに動物的な装置のように思われて、なんだかぞっとなった。あの頃の自分のように、今でも学生たちは飼育の果てに、与えられた娯楽をベースに仕込まれただけの自我をより所に、チープなエゴを発散させて、鶏小屋の生活を謳歌しているのだろうか。無駄な知識ばかりを、ノイローゼになるほど詰め込まれながら、それでいて真実を悟らずに、動物的なおしゃべりを繰り広げながら……
下りるべきステーションは、もう迫っていた。
人々の背中を見送ってから逃れ出た啓司は、空のベンチに腰掛けて、しばらくはうごめく人波を見送っていた。列車は消え失せる。遅れて改札を抜けたのは、鶏の密集から離れたかったからに違いない。おそらくは明日(あす)またここへ通う……そんな毎日の生活が、恐ろしい儀式のように思われてくる。
歩道へ逃れると、駅近くだけは繁盛していた。
書籍と喫茶店を過ごすと、眩しい看板の下で、
ビラ配りのアルバイトが、
「いらっしゃいませ」なんて呼び込みをやっている。
活気付けのために、変なジェスチャーを交えて、盛んにビラを配って、注目を浴びつつ手渡している。恐らく、この学生の行為は、この瞬間においては、自分のような鶏小屋の流れ作業ではないのだろう。自立的な愉快が籠もっている。こいつはきっと、まだ犬の自尊心を信じているに違いない。だが……
いくら、自立の犬といっても、
所詮は同じではないのか。
長年鎖に繋がれたなら、次第に精神が変化して、鎖と餌のもたらす生活のありがたみにはよだれを流し、最後には自我をさえ放棄してしまうのではないか。つまりはそれこそが、あがきの瀬戸際に溺れかけた、今の自分の苦しみなのかも知れない……
ビラ配りの奥では、階段が降りながら右に折れ曲がっていて、和風の居酒屋が扉を開いている。酒樽にパンフレットが載って、メニューが立て掛けてあった。ビラを持っていけば、駆けつけ一杯が無料なのか、半額なのか、それともお通し代がただなのか、そのへんは分からない。
啓司は無論留まらなかった。
歩調を変えずにやり過ごす。
一匹の猫が首を鳴らしながら、寒そうな路地裏へと消え去った。己(おの)がマイペースを突き進む、気ままな猫の散歩道。一方では、ポリシーを重視する自由意思の忠犬。それぞれの居場所。それぞれの仲間たち。本当は、そんな居場所を確保することこそが、生涯唯一の試練であり、また喜びでもあるのだろうか。自分はその試練を回避したばかりに、社会に封じ込められたのだろうか。職場での殺伐した毎日を思い描いたとき、眩しい都会の夜に代わって、陰鬱(いんうつ)が胸に覆い被さってきた。悪魔どもが闇を奪われた恨みとすればまだしも言い訳が立つが、この陰鬱は人の世が生み出した、人工の産物に他ならない。そんな取り留めもない感慨を抱きつつ、彼は歩調を早めるのだった。
彼はある国家試験を目ざしていた。
そのために、相当の歳月を準備に費やしてきた。もちろん大学の延長では無かったから、零からの学びとなった。ちょっと突き詰めるにしても、五年、六年はあっという間に過ぎてしまう。その間彼は、正社員の雇用は探さなかった。非正規のまま時間を確保しつつ、目標へと邁進(まいしん)したのである。だが独学だったので、中々はかどらない。ようやく試験を受けたのは、二十代も後半に入ってからのことであった。
始めて受験したときの緊張は今でも覚えている。登録を済ませるときにちょっと指先が震えて笑われた。自分より若い奴らが大勢いて、尻込みした様子さえ記憶に残っている。けれども受からなかった。初めての経験だから仕方がない、そう思い直した彼は、翌年また受け直した。今度は自信もあったが、やはり落第した。それから三度四度と踏み外すうちに、さすがに焦りが生まれてきた。五度六度と重ねても、やはり受からなかった。
三十代の前半は、それでも楽天主義が勝っていたような気がする。三十路の半ばを過ぎた頃から、危機感が高まってきた。第一仕事疲れで倒れ込むから、知識がさっぱり増えていかなかった。そのうえ誰とも話さない知識だから、どんどん抜け落ちていくらしい。そうやって落第を重ねるうちに、とうとう四十路が迫りつつあった。
精神と肉体の衰えを、始めて感じたのはいつ頃だったろう。
初めは予兆には過ぎなかった。試験への危惧が胸をよぎったが、気力がはるかに勝っていた。それが落第を重ねつつ四十が近づくにつれ、急速に膨れあがってくるように思われた。近頃では、どんなに頑張っても、社会から認められないような焦りが、挫折と一体になって胸を覆い尽くしている。すると、今までの努力すら虚しく思われて、どんなに心を奮い立たせても、侘びしさを宥めてみても、いっそう絶望の底辺へ、螺旋階段を下るような錯覚に囚われてしまうのだった。
あるいは目標が高すぎたのだろうか。
自分がいつしか靴を眺めているのに気がついて、
啓司は慌てて顔を向き直った。

信号が点滅して、人だかりを押しとどめる。
ヘッドライトが滑り出すと、排気音がむっと寄せてくる。
不意に夜風が払ったとき、肌寒の春のおぼろの、懐かしい田舎の気配が感じられて、思わずはっとなった。故郷の両親はどうしているだろう。二人とも家にいて、今は年金で暮らしている。困らない程度に自立しているが、無心を頼むほどの余力はない。いい年をしてそんな惨めな真似も出来ないから、思い切って今の仕事から、逃れることなど叶わないのだった。かといって、幾ばくかの預金をあてにして、先に辞めるのも憚(はばか)られる。啓司はちょっと苦笑いした。ようするに自分が、レールを踏み外すことを恐れているために、毎日こんな事ばかり考えるのだ。
今の職場は彼の目標とは関わりなかった。
正社員ではなかったが、彼は真面目に働いた。
三十を過ぎてから、正社員になれる機会があったが断った。頑固者の彼は、どうしても夢を諦めきれなかったからである。しかし歳月が落第を引き連れて流れ去るうちに、彼の心は蝕まれていった。ようやく近頃は、試験への挫折と、下り坂を迎えつつある自分の人生が、いち時に把握せられ、自分の終末が気になり始めた様子である。啓司は職場を逃れようとして、正社員の募集に探りを入れながら、最近では面接を繰り返しているのだった。
しかし、今さら正社員など夢物語かと思われる。
職歴の乏しさと、資格のなさに加えて、年齢の足枷がどれほどの束縛を加えるか、彼は初めて思い知った様子である。企業側が基本給の増加を避けて、中高年の正社員を雇おうとしないのだ。なるほど、それはもっともな話しかもしれない。だが、前時代的な風習にまみれた社会状況が、働き盛りの非正規を絶望の淵へと追いやっている。能力的な断罪によって首を切られるならまだしも、適正な人材を見抜けないばかりに、年齢で割り切ってしまうような企業体質が、今どき他の国にもあるだろうか。試験で落第を重ねたように、彼は面接も落とされる一方だった。
それにしても……この息苦しさは人間社会のそれではない。
あらゆる場合において、採択されないという事実が、社会から阻害されているような閉塞感となって、彼の心に覆い被さっている。信号と共に歩き出した啓司は、人をかき分けるようにして進んでいった。どしどし歩きながら、道を二三度折れ曲がると、ようやく駅前の盛りが遠のいて、ほっとするくらいの住宅地が控えている。
人通りを逃れて、外灯の列をとぼとぼ歩む頃、行き交うヘッドライトさえまばらになってくる。ちょっと気分が軽くなって、靴音を高くするゆとりも生まれてきた。つまりは人が多すぎるから、人でなしの鶏小屋に陥ってしまうには違いない。かの鶏小屋に十倍の広さがあったなら、あの欲求不満の鶏にしたって、小屋を出ようとはしなくなるかもしれない……そんなことを考えながら、項垂れている自分が滑稽だ。
滑稽、滑稽、こけこっこう。
不意に思いついたら、急におかしくって噴き出した。
慌てて辺りを見渡してひとりで照れてみる。ちょっと恥ずかしい。愁嘆(しゅうたん)から駒(こま)みたいな冗談を訝しがって、彼はもう一度「こけっこう」なんて反芻(はんすう)してみるのだった。
自宅も大分近づいてきた。
不意に眩しさが歩道まではみ出して、スーパーの照明が照らしてくる。
彼はちょっと立ち止まった。まっすぐ帰れば、すぐにマンションである。ぼんやり眺めていると、ひな祭りも過ぎたばかりだから、店頭の関連商材が撤去されて、チラシの目玉が並べられている。明日の朝市のためのポップを、店員が静かに付け替えているようだ。
どうしようかなと迷ったが、啓司は店頭へと折れ曲がった。仕事帰りのビールが冷蔵庫に入っていない。鞄が重いので、両手とも塞ぎたくはなかったが、酒がないとなると、物足りなさが募ってやりきれない。買わないで後悔するよりは……そう思って、入口へとすべり込んだ。
買物カゴに商品を投ずると、投ずる分だけ重みが増してくる。万有引力の法則。疲れた彼は、意味不明なことを考えながら、夜市として通路に出された、投げ売りトマトを一袋、意を決して掴み取った。安いはいいが、はなはだ重い。代わりにビールはまとめ買いではなく、ロング缶を一本で我慢する。レジでは若いアルバイトの店員が、
「いらっしゃいませ」
なんて丁寧なお辞儀をするのを、無視してすっと通過すると、慣れないせいだろう、丁寧におつりを数える仕草がのろまである。ここは自動レジではないらしい。フレッシュな態度に接していると、ちょっとだけ心が宥められるような気がするのだった。
サッカー台で商品を袋詰めしていると、パート・アルバイトの募集が、九百円からになっている。啓司の時給よりはずっと低いが、同じ時給制である。同じ非正規である。いっそ気分転換に、安い時給のスーパーにでも、働いてみようかなんて、自虐的な気分も湧いてくるのだった。正社員の面接はもう十社ほど落ちている。この歳にして大した数ではない。そんな気休めをしたって、やはりへこたれる。職場に内緒にしているのも落ち着かない。前の上司が移動してしまったから、社員登用も閉ざされたようなものだった。今の上司は、なるたけ安価な労働力を確保しようとする、ちんけな男には違いなかったからである。
「やれやれ」と思いながら、逃れる町並みは暗かった。
店の眩しさを浴びたせいで、なおさら暗陰(あんいん)が募るのだろう。
ヘッドライトは忙しないが、駅前でないから通りは少ない。両手を塞がれたままで、残り十分ほどの道のりを、トマトを購入した後悔がてらに帰ろうか。また奇妙な感慨に耽りながら、啓司は空元気に町を闊歩してみるのだった。
今日も職場では、いらいらの連続だった。
名目主義の矛盾が、いたるところに蔓延してる。
彼の職場では、正社員と非正規は別物である。朝礼も正社員には専用の別枠があって、非正規は有り難くも伝令を、各部署において後から拝聴いたすことになる。それでいながら、仕事の内容は何一つ変わらない。特に中高年の正社員には、ニュースを賑わすような、首切り労働者を批判する資格など持たないような、無能者ばかりが多く含まれるのだった。よくこれほど集められたものである。彼らは安住出来る領土で怠け癖を覚え、名目的な事柄を職務に差し替えて、驚くべき自由と怠惰とを、時に謳歌しているのだった。
正社員を眺めると、二十代の新人だけがあくせく仕事をこなしている。若者の批判など、いじけた中年世代に、ほざく資格なんかあるのか、どうしても肯定しきれない。特に四十代、五十代は悲惨である。存在意義すら疑わしいのが大分いる。なんの生産性にすら寄与していない。無意味な中間管理職に留まって、的確な指示すら出さず、すべてを非正規や若手に押しつけている。会社への存在意義がまるでない中で、誰も読まない計画書を記したり、誰に伝達するでもない、 手を打つでもない情報を、書き写したりして忙しがっている。純粋の歯車社会にしたって、こんな粗悪品じゃ、到底立ちゆかない。歯車社会を突き詰めるなら、ひとりひとりを最適な部品に選別して、部品の質に応じ、雇用形態を柔軟に、的確な賃金を支払うだけでも、つまり、表層的な合理主義を突き詰めるだけでも、どれほど効率がアップして、労働意欲を掻き立てるか分からないのに。
職場を幾つも巡った啓司には、これが今の職場特有の雰囲気でないことを知っていた。仕事の内容いかんに関わらず、一度正社員として取り立てられれば、どれほど無能を極めても、解雇に足るべき失態でも冒さなければ、手厚い保護に守られる無能力社会。一方でそこに登用されないとなると、どれほど優秀でも、ほとんど横並びの時給に陥って、惨めな社会主義的生活を余儀なくされるような絶望社会。現に彼は今、半分程度しか作業をこなさない非正規の同僚を、毎日使いこなしているのだったが、その賃金は、驚くほど格差に乏しかった。つまりは相応に認められる代わりに、平等にこき使われる全体主義。それが鶏小屋に蔓延する、どす黒い空気の元凶にさえ思えてくるのだった。
計画の実質的な采配を振るって、
無能な社員の世話まで行っている自分が、
近頃憐れでならなくなる。
少し前までは、そんなことは考えなかった。
自分の目標は、別にあって、
職場は賃金を稼いでいるに過ぎないと、
割り切っていたからである。
近頃、別のことを考える。
もっと、淋しい荒野のことを。
あの犬に話しかけた口の悪い鶏、
あれは自分ではないだろうか……
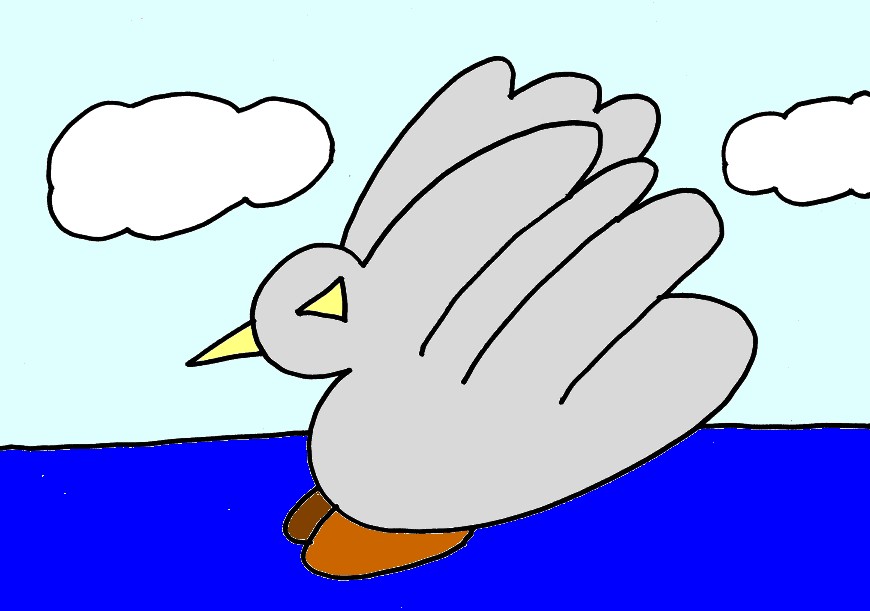
それにしても疲れた。
毎日頭をぐるぐる駆け巡る、怺えきれない哀しみが、ありきたりの幸せを拒絶するような気配である。それでいて、近頃、頭の切れが悪くなってきている。それは間違いない。年齢のせいだろうか。空気が悪いせいだろうか。ただいらいらばかりが募って、何もかもが面倒で、訳もなくケリを付けたくなってくる。そのケリは、明確な方針へと帰結するようなケリではなくって、ただ現状を逃れたいがあまりに思い詰め、思い詰め、その実、行き場なんかどこにもない、絶望的なケリには違いなかった。この気持ちを知らないうちは、四方を壁で囲まれて、何をやっても跳ね返されるような虚しさを、それが永久(とわ)に続くような虚しさを知らないうちは、きっと何とでも言えるんだ。だが、このケリが、逃げ場を失ったとき、どす黒く心を染め抜いたとき、往々にして人を死に際へと導くことを、今の啓司ははっきりと悟ることが出来たのである。
街灯の下を潜ると、影法師が前に来る。
二次元の住人がおどけた影絵みたいに、手足をばたつかせている。とても自分を反映したものとは思えない。靴音は自分ではなく、彼が高鳴らせているのだろうか。もし彼が自分と入れ替わってくれたなら、この閉塞感から抜け出せるだろうか……なんて考えているうちに、あまりの馬鹿らしさにまた苦笑した。
近頃、人と話さない。
人と話さなくなってから、いつわりの会話でさえも、まだしも心を支えていることに気がついた。学生時代の知人とも、随分前から疎遠になってしまった。何があった訳でもなく、ただ、ひとりふたりと連絡が途絶えて、宵闇へと帰されただけのことである。要するに互いに忙しすぎるのだ。彼の労働時間にしたって、残業を含めると、正社員とほとんど変わらないくらいである。かといって職場では、皆をまとめるテキパキ口調になるから、まわりとは確執が生まれてしまう。親しむべき相手とは見なされず、いきおい仕事の話しばかりになってしまうのだった。
……自分は生涯、こうやって生きていくのだろうか。
語らうべき恋人すらいない。
さみしい思いがないでもなかったが、
今さらどうにもならない気がする……
遠くで列車の音が響く。
自分の終着駅もそろそろ見えたかと思う。
近頃、精神が沈み込んでいる。思い詰めたせいで、悲しみの風船が肥大して、こころをすき間なく覆い尽くしているような気配である。人と交わらないのが原因だろうか。それとも非正規から逃れられないせいだろうか。面接を受けても、試験を受けても、阻害され続ける虚しさだろうか。あるいは年齢……
彼は思わず頭を振った。
この頃よく考える。
生まれてこなければ良かった。
そんなことばかり思い詰める。
眠っている時でさえ、閉塞感に追い立てられるような、おぞましい夢を見ることがある。こうして宵の街を歩きながら、闇をさ迷うような錯覚に囚われるのだ。今は両手が重くて仕方ないんで、なおさらやりきれなさが募るのだろう。思わず立ち止まると、ようやくマンションまで辿り着いていた。
外鍵を開くとき、なぜだか分からない、
彼は不意に、あの鶏の末路を思い描いた。
それは、あの犬の采配により、静かな満月の夜に、一羽分の逃げ道を確保して貰った鶏が、そこから抜け出そうか、そのまま留まっていようか、夜通し考えているという結末だった。そうしてそれより先、どうしても帰結は浮かんでこないのだった。
(おわり)
作成
[2010/5/18-20]
(原稿用紙換算35枚)