つきみ酒
2014年と2015年の落書から、掲載に足りそうな発句と、それにまつわる文章を拾いました。それから章の最後に散文が来るように、足りない言葉を補いました。おまけにお絵かきもしてみます。ただそれだけの宵でした。
去年今年
はせをの発句をひもとくうち、つらぬく棒のごとき比喩の、おろそかなるには羞恥を致し、
「浅薄なるかな吾。拙劣なるものを、
あがめたてまつりし時もありき」
など、煩悶と興ざめをカクテールすれば、
去年今年
貫く棒の 如きもの
文芸とも至らぬほどの矮小さと、それをひけらかす自我(エゴ)、「貫く棒」のあけつぴろげにはなみだをながし、その比喩ます/\あさましく響く夕べには、ミクロコスモスと塵芥(ちりあくた)の区別もつかぬ乏しさを、小市民的傾向へと移し換え、朽ちた枯葉とありがたがるほどの、しぐれにうたれるみじめさを、吾らひとり/\はたそがれに、さみしく滅びゆくものだとしても、それでもこゝろのうちには、彼らとは違う星のひとかけら、きらめきくものと知るならば………
はしまりと
をはりませかふ 鐘も又……
もはや「鐘の音」やら「除夜の鐘」などのフレーズも、マンネリズムの堆積に、うずもれるばかりの砂丘には、こころのかけらもあらざる事を悟るとき………
「大つごもり」
おはり瀬に
はじまる波の音あらむ
くらいの空想もまた、
棒よりはまだしもゆかいに感ずるばかりなるべし。
元旦 書生記す
[棒の如きは、警句を反復するときのよろこび、力強くて明快ないい切り方がもたらす爽快さと、単純な発想のもたらす愉快があり、そうしてそれ以外はなにもない。俗人受けするのはもっともで、引き合いに出されるのももっともで、語られがちなのももっともではあるが、それは警句としての愉快さであって、詩情とは関わりの浅いものである。情に乏しいのではなく、情に浅いのは、時間軸の比喩として、棒というのが、はなはだ安っぽく感じられるからであり、それ以外のなにものでもない。俗人は、強い刺激をありがたがるものである。ならば、この句の価値も、保証されたと言うべきか。]
春の歌
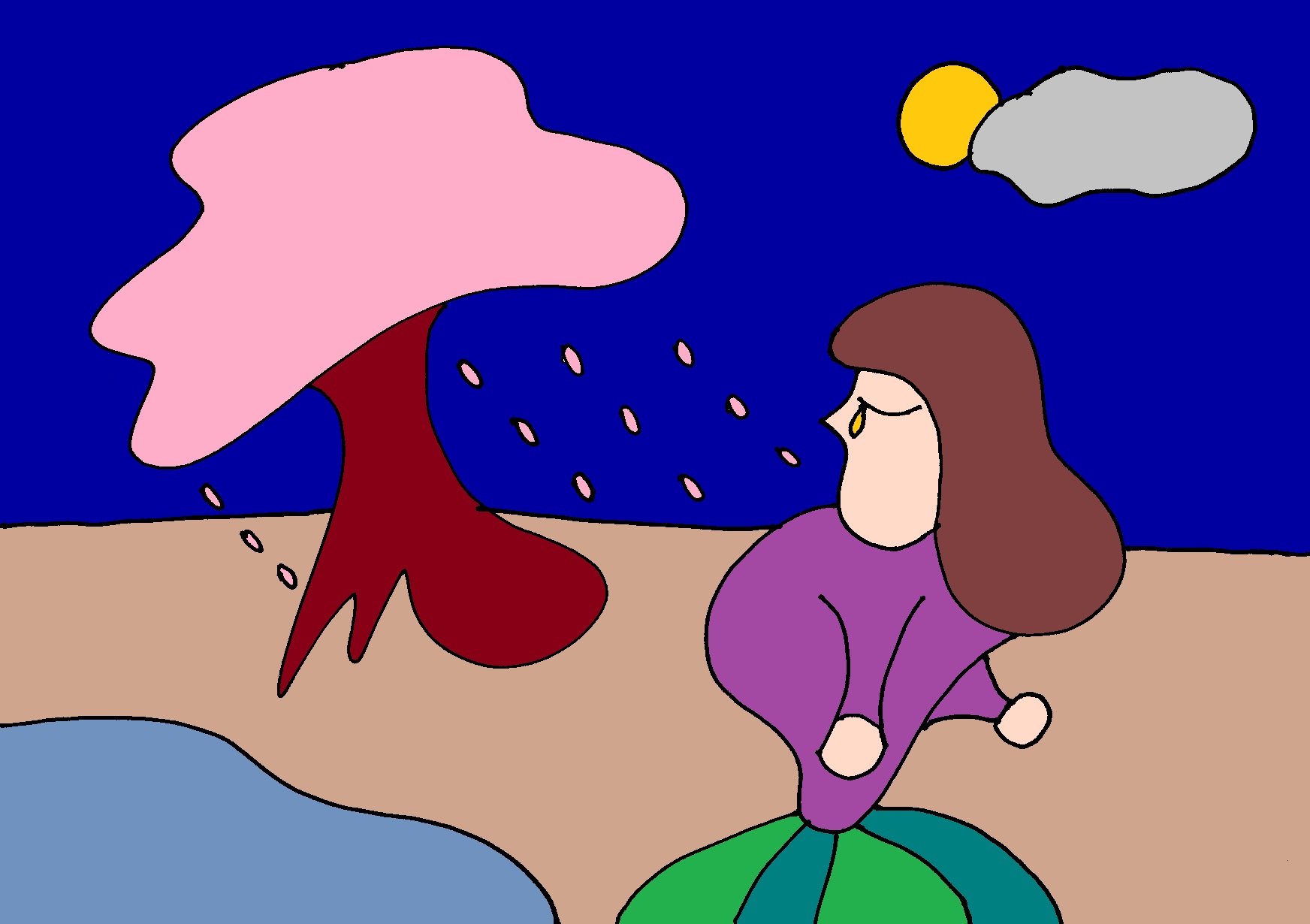
返されて
ショコラーデした なみだかな
酔わされて
だまされたくて はしゃぎ猫
さくらして
風になみだの 散る夜かな
[「風に」⇒「風は」]
ポニーテールの唄

駅へ向かえば、小学生くらいの女の子たち、はしゃぎながらすれ違う時に、何気なく思いつくことは、
通学路
風にリボンが もつれては
思いつきならば、そのままの表現はよろこばしく、けれども句にもならないことは、また当然のことならば、
通学路
風にリボンが もつれ歌
など、空想的な表現にゆだねて、駅の階段をのぼる頃、
ポニーテール
風にリボンが もつれ唄
通学路を捨て、代わりに迎えた「ポニーテール」がここちよく思われたので、これを端末に書き留めて、駅の改札を抜けるのだった。けれども………
「もつれ唄」というのは、空想的傾向に勝るものとして、現実的にものすならば、
ポニーテール
風にリボンが もつれ髪
くらいになるだろうかと思い比べる時、わざわざポニーテールと風とリボンを持ち出した、その絡み合うようなうれしい感じが、「もつれ髪」だと理屈に落ちて、なんのおもしろみもなくなることに気がついた。つまり空想的に「もつれ唄」としないと、上句も中句も存在する意味がなくなってしまう。ポニーテールを付けているはずの誰かの心理状態が、最後の「もつれ唄」には込められていると気がついて、「もつれ唄」をもって完成とすることとした。
夏の歌
[はじめここに、
「どんな夢を
僕らに明日を 虹のさき」
という駄句あり。みせしめに記し置くものなり。]
こぽ/\と
おどる清水を 呑みにけり
とうせんぼしかけ花火のラプソディ
あまやどり

言葉の動くとき、言葉の置き換わるとき、句は完成していないとされるが、どちらの意味でも価値が認められ、どちらが劣るほどのものでもないならば、あえて確定させる必要などないのかもしれない。たとえば、帰省するあいだに列車に揺られながら思いついた句に、
手を振るは
傘待つ君か あまやどり
というのがあるが、中句の動詞を名詞化させて、
手を振るは
傘待ち君か あまやどり
とすれば、手を振る相手が、ちょっとキャンバスに描かれたような、アルバムの一葉じみた気配がこもる一方で、初めに見られた、即興的な臨場感が、ちょっと遠のくようなもの。どちらがよりすばらしいというほどのこともなく、同質的傾向が顕著(けんちょ)である。あるいはこれを、
手を振れば
傘待ち君か あまやどり
と改編すれば、手を振るのが相手から、読み手自身へと移され、内容は大きく異なるにも関わらず、どちらの解釈にも意義とおもしろみがあって、それぞれが天秤の釣り合って優劣をつけられないならば………
これらの作品は、すべてが完成品であるとして、三つ並べても差し支えのないものである。矮小な傾向の籠もるわずか十七字において、たった一つの完成された小宇宙が存在し、それこそ芸術であるなどと思い込むのは、いくらなんでも蟻ん子の脳みそにすぎるだろう。
秋の歌

まぼろしの
みやこあそびよ かぐやひめ
清らかに 照る月なみの ふたりかな
いのり火
夜半に吹き消す 嵐かな
君は去り
夕んべな風よ はぎの月
君去りて 虫鳴きしきる 夕べかな
かゞりやんで
風に散りしく もみぢかな
夢を背に
いざよふ汽車を 聞く夜かな
ほされて
さらされ朽ちる そほどかな
使いまわしのフレーズ
ふるさとは
とほく/\て しぐれかな
わずか十七字であればこそ、ここちよいフレーズのパターンに、さまざまなシチュエーションを折り込んで、あちらの情緒、こちらの情景をゆだねたくなるのは、なにも盗用を持ちだすまでもなく、故人の表現のうつしかえが、砂利の連なっているようなこの道程を眺め返すだけでも、理解できるかと思われる。もちろんそれには、矮小なマンネリズムの問題も含まれるだろうが、本質的に短い表現を警句的に、類型的なフレーズにゆだねたくなるのは、むしろわたしたちの会話の本質から導き出された、パターンのここちよさが関係しているのかもしれない。たとえば、この句などは、すぐ後の雪の発句にも、
しろく/\
しろく/\て ゆきあかり
先のパターンに、さらに同型反復のパターンを加えて、まさに語りのここちよさに身をゆだねたような表現も見られるし、そもそも「とほく/\てしぐれかな」という表現自体が、
冬の海遠く遠くてあかりかな
という、もっとも初期の俳句集『幸子へ、あるいは四季の夢』から来ているのは、単純にこのはじめの俳句が、こころに何度もリフレインされるうち、お気に入りの表現として、たびたび顔をのぞかせるに過ぎないという、それだけのことではあるのだが……
それにしても、「ちかく/\て」だろうと「あかく/\て」だろうと、さまざまな形容を当てはめて、その対象を「~かな」で締めくくるだけなら、その発句のアイデンティティが心配されるかもしれないが、実際にこのパターンに当てはめてゆかいなものなど、この世には数え切れないほどある訳で、橘曙覧の「たのしみは」を出すまでもなく、いずれにせよ一定の情緒を宿すならば、類型的であるからといって、軽蔑するほどのことはないかと思われる。それに……
これほど短い表現に、個別的な絶対的個性など打ち立てようとするから、詩でも何でもない頓知と屁理屈に、不可解な表現を織り交ぜた、あまたの落書きが今日もまた、生みなされているのではないでしょうか。
冬の歌

あかぎれにひかれてはしゃぐふた子かな
差し伸べて 星につゞみを 打つ夜かな
あわゆきの
なめてはやせる 犬っころ
おしゃべりなペチカ
狼のうなり声
しろく/\
しろく/\て ゆきあかり
うずもれるポチの御墓よゆきあかり
千代が梅の
枝落しけり しづり雪
千代が枝の
夢落しけり しづり雪
ではいと安し
今はむかし
むかしは雪に 染まりゆく
ふんわり
ふとんにくるまる ゆきおんな
雪の夜 ― 動くという事につきて

動くということにつきて。容易に置き換わる言葉は、詩の定まらぬ証なり。他にも配置の動く事在り。同じ意にて、言い換えの利く事在り。よく/\尽くすべし。
ロウソクの灯しも尽きて雪あかり
居酒屋の灯しも尽きて雪あかり
君の窓ともしも尽きて雪あかり
言葉も配置も、いかようにも移り変るは、着想の未熟による処なり。最後の如き惰弱の情緒は、現代語こそ勝るべし。
ともし消えて君の窓辺よ雪あかり
雪あかりともし火消える君の窓
句の善し悪しはさておき、ひと文字動かせば、又意味も変るなり。
雪あかりともして消える君の窓
暇をもてあそぶが如く、着想の変るも面白し。至らざる落書のうちにも、以下などはあへて季語を必要とせず。
ともしする窓辺に消える君の影
さりとて季語を込めたれば、浮かび来たる情景の、たやすく情緒へと至るべし。
星冴えてともし火消える君の窓
雪あかりのふと消されたればこそ、
もとの着想の安易を思い知るべし。
窓よりも又、
星冴えてともし火消える君の家
もとより居士の時代なれば、
星冴えてともし火消える君が家
この「の」と「が」にはそれぞれ意味の籠もるなり。
さりとてはじめの雪も捨てがたきとすれば、
雪ふかみともし火消える君が家
などは、星と灯火のあからさまなる対象を捨て、おだやかな冷たさに包みこむが如し。かくの如き対象のうつろひは、畢竟(ひっきょう)写実のうちにものせず、空想にものしたるがゆえに起こることにて、現実なればこそ万人に受け入れられるがゆえに、実写はたやすく、空想は困難なるべし。しかれども、実写にせよ、空想にせよ、言葉は動かぬ処まで、よく/\吟味すべきにや。
(書生記す)
四季の歌

なっぱして
四季折々な お漬けもの
消されず……
あふれる宵は かなしみと
くゆらせて時折むせぶパイプかな
マニエリスムの
果てにまどろむ 鴉かな
みづうみの
影さへあせて うすあかり
君見ずや
ほの燃えわたる かゞり火を
つきみ酒

カクテルの紹介に発句でも加えようと思って。
銀のうさぎ 金のしづくか つきみ酒
これは、「銀のしずく、あるいは金のうさぎのようにも見える月を、眺めながらに酒を飲む」くらいの思いを、ちょっとした修辞に交差させた落書には過ぎません。つまりは、
銀のしずく 金のうさぎか つきみ酒
という着想を、ひねったようなものなのですが、あるいは、
銀の鈴
金のうさぎか つきみ酒
のほうがよいのか、あるいは、
銀のうさぎ
黄金のしずく つきみ酒
がよいかなど、何度も繰り返し、どれほど唱えても、最終的にはある特定の表現へと、理想が収斂(しゅうれん)されるとき、
銀のうさぎ
金のしずくか つきみ酒
こそが詩として、落書以上の価値を有すると、わたしにはようやく判断されるものでした。たとえばこれが、百年を超えて通用するならば、発句は芭蕉へといたるでしょう。数年のうちに陳腐化するならば、一茶の虚名はまぬがれないかもしれません。さながら猥雑(わいざつ)な落書のなかに、ときおり原石が転がるようなものかもしれません。
もっとも、蕪村には見どころがあるでしょう。
子規はまことを探求し、蛇笏の表現は、
感性とかみ合っているように思われるのですが……
それにしても、虚子の後半生は、
蛇足のように思われはしませんでしょうか。
それさえまだしもマシに思われる頃、あふれかえるものは、世のなかから遊離したような、路傍に転がる蝉どもの、近づけばいきなり人を驚かせるような、警句にあふれた言葉遊びやら、メディアに群がるような、点取り先生やら生徒ども、利権をむさぼる企業との、枯葉をまとったような、collaboration 舞踏会。そんなものが、芭蕉の夢の残骸みたいにして、腐気(ふき)を放ってはいないでしょうか。
(おはり)